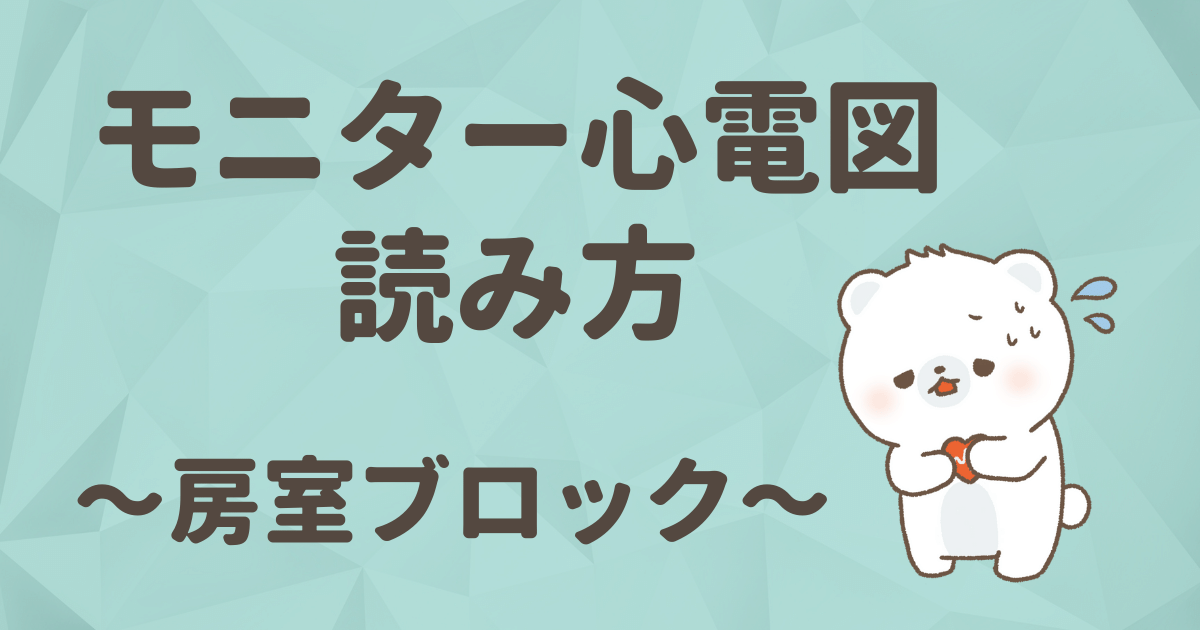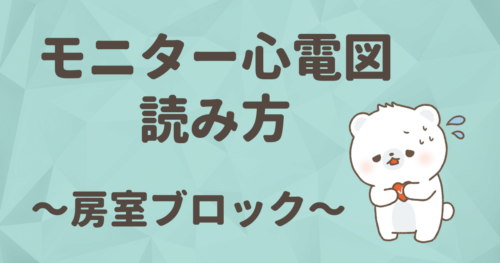今回は房室ブロックについて解説します。
房室ブロックは障害の程度により以下のように分類されます
- 1度(伝導遅延のみ)
- 2度(間欠的に伝導途絶)
- ウェンケバッハ型(Wenchebach型、Mobitz 1型)
- モビッツ型(Mobitz 2型)
- 高度(2:1伝導や、連続して途絶する場合)
- 3度(完全に伝導途絶)
第2章で説明したように、心電図にて房室伝導を表す部位はPQ間隔でした。
PQ間隔に注目しつつ具体例をみていきましょう。
目次
1度房室ブロック
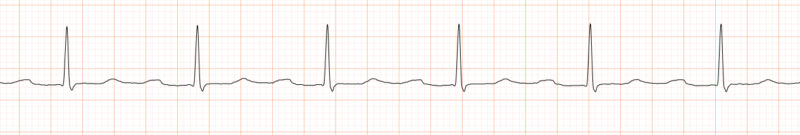
- 規則正しいP波がある
- PQ間隔は一定だが延長している(200msec以上)
- QRS波の脱落はない
ウェンケバッハ型2度房室ブロック(Wenchebach型、Mobitz 1型)
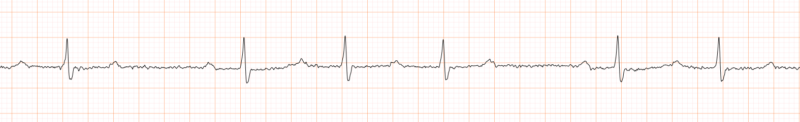
- PQ間隔が徐々に延長して、QRS波が1拍脱落している
- 連続して脱落することはない
モビッツ型2度房室ブロック(Mobitz 2型)
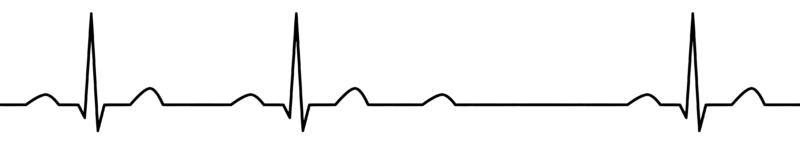
- PQ間隔の延長を伴わず、突然QRS波が1拍脱落
- 連続して脱落することはない
高度房室ブロック
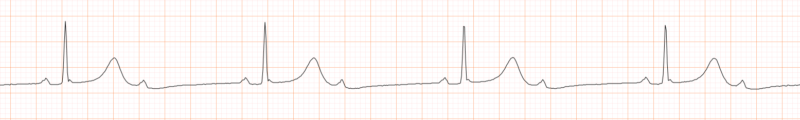
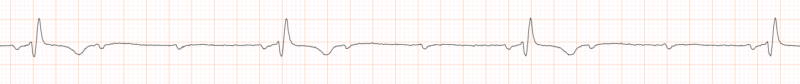
- 2回に1回の頻度で脱落する(そのためウェンケバッハかモビッツかの判定ができない)
もしくは
- 2回以上続けてQRS波が脱落する
3度房室ブロック(完全房室ブロック)

- 規則正しいP波がある
- RR間隔は整、PP間隔も整だが、それぞれの間隔が異なる
- そのため、心電図上PQ間隔はバラバラになっている